法人破産で社会保険料はどうなる?滞納リスクと対処法まとめ
法人破産
2025 . 04.28
法人破産
2025 . 04.28
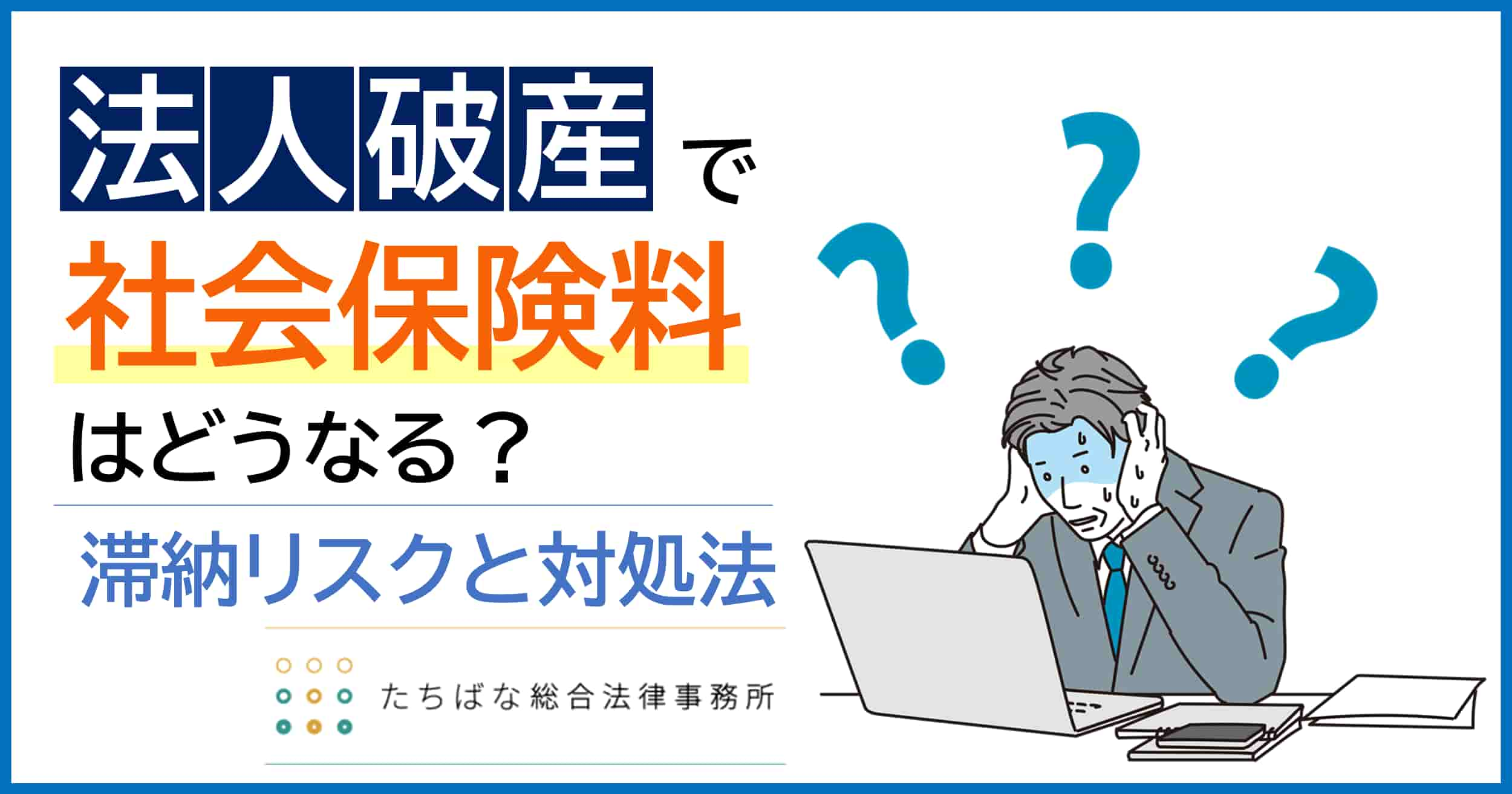
この記事でわかること
 たちばな総合法律事務所 代表
たちばな総合法律事務所 代表 たちばな総合法律事務所
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
目 次
法人破産に至った場合、社会保険料はどのように扱われるのでしょうか。
法人と個人では破産後の責任の範囲や支払い義務が大きく異なります。
まずは基本的な仕組みと全体像をつかむことが重要です。
本記事では、法人破産時における社会保険料の基本的な扱いから、破産手続きの配当手続きにおける滞納税金の優先順位、法人破産時に代表者に納税義務が及ぶ可能性や責任の範囲について詳しく解説します。
結論から、法人破産により法人格が消滅すると、それと同じく未払い・滞納している税金も消滅します。
破産手続きにより、権利義務の帰属先である法人格が消滅するためです。
今回の社会保険料だけでなく、下記に該当する公租公課は破産手続きにより法人格が消滅するとともに、支払い義務も消滅します。
参照 法人破産手続き終結により消滅する、破産会社が納税義務を有する公租公課の例
・法人税(税務署)
・法人府民税・県民税(府税事務所・県税事務所・地域振興局)
・法人等市民税・町村民税(市税事務所・市区役所・町村役場)
・法人事業税(府税事務所・県税事務所)
・固定資産税・都市計画税(市税事務所・市区役所・町村役場)
・源泉所得税(税務署)
・特別徴収市府民税・町村県民税(市税事務所・市区役所・町村役場)
・消費税・地方消費税(税務署)
・健康保険料・調整保険料・介護保険料(社会保険事務所・保険組合)
・厚生年金保険料・児童手当拠出金(社会保険事務所)
・厚生年金基金掛金(厚生年金基金)
・労働保険料(労働局)
・国民健康保険料(市区役所・町村役場)
・自動車税(府税事務所・県税事務所)
・軽自動車税(市税事務所・市区役所・町村役場)
・地方自治法に基づく分担金(市区役所・町村役場)
法人破産とは、会社が多額の負債を抱え、経営継続が困難になったときに裁判所の関与のもと行われる倒産手続きの一つです。
破産手続開始後は、裁判所が選任した破産管財人が財産を整理し、債権者に公平に配当が行われます。
最終的には法人格が消滅し、会社そのものが法律上存在しなくなる点が特徴です。
法人破産は、まず経営者や債権者が会社の破産を申し立てることから始まります。
裁判所で破産手続の開始が決定されると破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産会社の資産や負債の実態を把握するための調査や、保有財産を換価し、得られた資金を債権者に分配する手続を進めます。
参照 破産管財人の主な業務内容
① 財産の換価・回収(破産財団の増殖)
② 債権調査手続き
③ その他法律関係の処理(物件の明け渡し、口座の解約など)
④ 配当手続き
このとき、税金や社会保険料などの公的負債には一定の優先度が認められています。
参照 配当にあたっての優先順位
1 破産管財人の報酬
2 優先的破産債権のうち
「国税・地方税(公租)」
3 優先的破産債権のうち
「私債権(労働債権;従業員の未払給料など)」
4 一般破産債権(借入金など)
5 劣後的破産債権
6 約定劣後破産債権
最終的に配当が終わると、法人としての人格が正式に消滅し、会社は解散します。
この時、残っている公租公課含め負債は全て消滅します。
会社が雇用している従業員が加入している健康保険や厚生年金は、事業主と従業員がそれぞれの負担割合を負って保険料を納める仕組みになっています。
法人はこれら社会保険料の負担分を求められ、滞納が発生すると強制徴収のリスクが生じます。
また、労災保険や雇用保険も同様に会社が手続き・納付を行う義務を負います。
これらの保険料費用の滞納が続くと追徴金や延滞金などのペナルティも発生します。
法人が破産に至る際には、それまでに発生していた社会保険料の支払い義務もまとめて清算対象となります。
ただし、例外的に、一定の場合には代表者個人が法人の滞納税について納税義務を負う可能性があるので注意が必要です。
次に「代表者個人に納税義務が生じる」注意すべき3つのケースについて解説します。
① 個人事業者が破産する場合
② 合名会社の無限連帯責任
③ 第二納税義務が生じる場合
個人事業者は、法人格を持たないため、事業主である個人と事業は一体とみなされます。したがって、個人事業者が破産した場合、それは事業主個人の破産となります。
■ 当コラムにおける「法人破産」「個人破産」の用語の区別
「自己破産」とは、本来は法人、個人の区別なく裁判所における破産手続きの総称です。
ただ、当コラムでは、法人の破産と個人の破産手続きを区別して説明するために、株式会社、弁護士法人といった「法人格」をもつ法人の破産申立(法人破産)に対して、個人の方(個人事業者を含む)の破産手続きについて「個人破産」と表現しています。
個人事業として生じた滞納公租公課は、事業主個人の債務として扱われます。
自己破産において、個人の方が免責許可決定を受けても支払い義務がなくならない債権を「非免責債権(ひめんせきさいけん)」といいます。
これは破産法第253条1項に定められています。
税金や公租公課は非免責債権に当たります。
そのため、たとえ破産手続きにおいて免責が認められたとしても、原則として破産手続き終了後も納税義務は残ります。
ただし、自己破産の手続きとは別の制度・措置として、生活保護を受給しているなど、経済的に著しく困窮している状況にある場合、税金や国民健康保険料などについて、各自治体の条例や国の制度に基づき、申請によって減額や免除、または納税の猶予が認められる場合があります。
この減免・猶予の制度は、お住まいの自治体や税金の種類(市民税、国保料など)によって基準や手続きが異なります。
もし滞納税金の支払いにお困りで生活保護を受給されている、あるいは受給を検討されている場合は、役所の税務課や福祉事務所に相談し、税金等の減免・猶予制度について確認することをおすすめします。
合名会社や合資会社の無限責任社員は、会社の債務について無限の連帯責任を負います。
そのため、会社の財産だけでは債務を完済できない場合に、社員個人の財産をもって弁済する責任があります。
そのため、会社が自己破産した場合、会社の滞納公租公課についても、無限責任社員は連帯して支払う義務を負います。
会社の破産手続きによって会社の納税義務が消滅しても、社員個人の連帯責任に基づく納税義務は残ります。税務署は、法人破産後の無限責任社員個人に対しても納税を求めることができます。
会社の債務に対する無限連帯責任の一部としての納税義務(会社が払いきれなかった税金や第二次納税義務)を含め、無限責任社員がその責任を「免れる」一般的な方法はありません。
ただ、法人破産によって無限責任社員が財産を失い、収入もなくなり、生活保護を受給する状況になった場合、残っている納税義務(過去の所得税や住民税、あるいは第二次納税義務として引き継いだ会社の税金など)について、事実上の徴収猶予や換価の猶予、最終的な債務消滅の可能性はあります。
これは「納税義務の免除」というよりも、「徴収の猶予」や「滞納処分の停止」といった手続きになります。
☑ 滞納処分の停止
税金に滞納がある場合、税務署は財産の差押えなどの滞納処分を行う権利があります。
しかし、生活保護を受給しているような、滞納者に滞納中の国税を納付し、またはその財産によってこれを完納することができる見込みがないと認められる場合などには、税務署長の職権で滞納処分の停止を行うことができます(国税徴収法第153条)。
この滞納処分の停止が3年間継続した場合、その税金は法律上、納付の義務が消滅します。
☑ 申請による換価の猶予
財産を換価(現金化)されると事業の継続または生活の維持が困難になる場合に、一定の要件を満たせば、申請により差押えを受けている財産の換価等が猶予される制度もあります(滞納国税等の納付は必要)。
生活保護を受給しているということは、資力に乏しく、差押えるべきめぼしい財産もない状態であると判断される可能性があります。
この場合、税務署は現実的に税金を徴収することが困難であるため、上記の「滞納処分の停止」などの措置をとることがあります。
したがって、「納税免除申請」という直接の制度名ではありませんが、生活困窮(生活保護受給)を理由に、税務署に対して納税の猶予や滞納処分の停止を求めることはできます。
これが認められれば、事実上税金の徴収が行われず、一定期間経過後に債務が消滅する可能性があります。
第二納税義務とは、本来の納税義務者(この場合は法人)が納税できない場合に、一定の要件を満たす第三者が代わりに納税義務を負う制度です。
参照 第二次納税義務の根拠条文等
国税については国税徴収法第34条(法人の財産を無償又は著しく低い価額で譲り受けた者等の第二次納税義務)、第35条(同族会社等の第二次納税義務)、そして代表者の第二次納税義務については実質的に国税徴収法第39条(清算人等の第二次納税義務)の考え方が適用されることが多いです(破産手続きに入ると、破産管財人が清算人等に近い立場になるため)。地方税についても、地方税法に同様の規定があります。
また、社会保険料については、健康保険法、厚生年金保険法などに同様の代表者に対する納付義務の規定があります(健康保険法第75条、厚生年金保険法第82条など)
一定の要件を満たす例として、破産法人の事業を、代表者個人や生計を一にする親族にタダ又は不当に安い値段で譲渡して、事業が継続されている場合があります。
この場合、事業を譲り受けた者は、第二次納税義務者として、税務署から法人が負担していた税金(法定納期限より1年前以降の税金)の支払いを求められる可能性があります。
また、代表者個人が、法人の各種申告漏れや脱税などをおこない、税務署に法人の税金納付の期限を猶予、分納を依頼するために納税保証書を提出している場合や保証人となっている場合には、法人破産後においても、代表者個人が税金を納める義務が生じることがあります。
さらに、代表者個人が破産して免責決定を得ても、納税保証した場合の支払義務は消滅しないので、注意が必要です。
法人破産は、そこで働く従業員にとって大きな影響を及ぼします。
特に、給与の支払い停止に加え、雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)の滞納は、少なからず影響が生じる可能性があります。
雇用保険や年金手続きなどの正しい対応を把握しておく必要があります。
まず重要な点として、会社(法人)が滞納していた社会保険料の支払い義務が、従業員個人に直接引き継がれることは原則としてありません。
社会保険料の納付義務を負うのはあくまで法人であり、法人が破産手続きによって消滅すれば、原則として法人の負っていた債務(滞納社会保険料を含む)も消滅するためです。
しかし、会社の社会保険料の滞納や、破産に伴う手続きの遅れは、従業員の方々に以下のような実務上の影響を与える可能性があります。
法人が破産すると、従業員は職を失います。
雇用保険に加入していれば失業給付を受けられますが、手続きには離職票の交付や雇用保険被保険者資格喪失手続きなどが必要です。
■ 雇用保険(失業給付)
会社が破産し従業員が離職すると、原則として雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格を得られます。
受給のためには、会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、従業員に「離職票」を交付する必要があります。
これらの書類が迅速に発行されないと、失業給付の申請や受給開始が遅れることになります。
倒産や解雇による離職は会社都合退職となるため、自己都合退職の場合のような3ヶ月間の給付制限がなく、ハローワークでの手続き後、比較的早期に受給開始できる可能性があります。
健康保険と厚生年金は会社単位での加入となるため、会社が破産や解散手続きに入ると従業員は強制的に資格喪失となります。
会社が適切に資格喪失手続きを行わないと、従業員が次の職場で保険に加入する際にトラブルになる可能性があります。
すぐに国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になるので、時間的猶予がない点に注意しましょう。
■ 健康保険
会社が健康保険の適用事業所でなくなると、従業員は健康保険の被保険者資格を喪失します。資格喪失後は、以下のいずれかの対応が必要です。
・お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する。
・以前加入していた健康保険を任意継続する(一定の条件を満たす場合。通常最長2年間)。
・家族が加入している健康保険の被扶養者となる。
会社は従業員の健康保険被保険者証を回収し、年金事務所等へ返却する必要があります。この手続きが遅れると、新しい保険証への切り替えが遅れたり、場合によっては古い保険証が使用できなくなったりするなどの混乱が生じる可能性があります。
■ 厚生年金
会社が厚生年金の適用事業所でなくなると、従業員は厚生年金の被保険者資格を喪失します。
次の就職先が決まっている場合は、新しい職場で厚生年金に加入します。
すぐに就職しない場合は、ご自身で国民年金への切り替え手続き(種別変更)を行う必要があります。会社から発行される資格喪失証明書が必要になる場合があります。
過去に会社が適切に厚生年金保険料を納付・届出していなかった場合、将来の年金受給額に影響が出る可能性もゼロではありませんが、基本的には国の制度として従業員の記録に基づき処理されます。会社の滞納分が従業員に請求されることはありません。
上記のように、従業員が法人破産後に転職活動を行う際には、離職票や年金手帳、健康保険の資格喪失に関する書類などが求められます。
これらの書類の記載内容の正確性や、発行の遅延は、転職先での手続きや社会保険への加入に支障をきたす可能性があります。
従業員が法人破産後に転職活動をおこなう際には、離職票や年金手帳、健康保険の資格喪失に関する書類などが求められます。
これらの書類の記載内容の正確性や、発行の遅延は、転職先での手続きや社会保険への加入に支障をきたす可能性があります。
経営者や破産管財人には、破産に伴い離職する従業員が速やかに次の生活への移行を進められるよう、法的に定められた雇用保険や社会保険に関する資格喪失手続き、および必要書類(離職票、資格喪失証明書など)の発行を遅滞なくおこなう責任があります。
従業員の不安を最小限に抑えるためにも、破産手続きの状況と並行して、これらの手続きに関する丁寧な説明と迅速な対応に努めましょう。
また、社会保険料とは異なりますが、未払いとなっている賃金については、破産手続きの中で財団債権や優先的破産債権として他の債務より優先的に扱われたり、会社の資産状況によっては国の未払賃金立替払制度を利用して、未払い賃金の一部または全部の支払いを受けられる場合があります。
これらの制度についても、従業員へ情報提供を行うことが望ましいでしょう。
社会保険料や税金の滞納が続くと、どのように差押えなどの処分が進むのでしょうか。
差押えは、債権者となる公的機関が強制的に滞納分を回収するための手段です。
銀行預金や売掛金、不動産など、会社が所有する資産を差し押さえて換価し、未払い分に充当します。
地方裁判所への破産申立てにも裁判所への予納金などの費用がかかるため、売掛金や保有資産への差し押さえを受ける前に、手元資金が残っているうちに弁護士に相談し早めに対策を講じられることをおすすめします。
社会保険料や税金が滞納している場合、各公的機関は会社の資産状況を把握するために財産調査を行います。
銀行口座や不動産登記、車両、売掛金など詳細に調べられることが一般的です。
調査後、滞納状況が深刻であると判断されると、督促状が発行され、法的に設定された期間内に支払わない場合は差押え手続きに移行します。
督促状の放置は事態の深刻化を招きます。
経営が厳しいと感じた時点で、相手方となる公的機関に相談や分納の申し入れをすることは可能です。
破産を考える前でも、なるべく早期に交渉し、差押えを回避できる手段がないか検討を進めるとよいでしょう。
差押えの対象は多岐にわたり、会社名義の不動産、自動車、動産や売掛金、預金通帳の残高などが含まれます。
そのため、差し押さえにより事業継続が困難になる可能性が高いです。
差押えを回避するには、早めに分納計画を提出するなど、公的機関との協議を進めることが効果的です。
また、会社経営者や債権者の合意のもとリスケジュールを行う場合もあります。
しかし、根本的に返済できる見込みがない場合は、破産手続きや他の法的整理を検討する必要があります。
最後に、法人破産と社会保険料の扱いに関するポイントを簡潔に振り返ります。
法人破産が開始されると、法人自体の債務である社会保険料の負担は基本的に消滅します。
ただし、無限責任社員であったり納税の分納の差し入れ書の有無によっては、破産後も個人が支払義務を負う可能性がある点に注意が必要です。
社会保険料の滞納があり、事業継続の目途が立たない、あるいは廃業しようとお考えの方は早めに弁護士に相談をして対策を進めることをおすすめします。
たちばな総合法律事務所では、法人の破産・廃業や生活再建に向けた個人の方の負債整理(個人再生・自己破産・任意整理)についてサポートしています。
破産管財人の経験を持つ、解決実績たしかな弁護士が相談から手続きが終結するまで、しっかり対応いたします。
弁護士にご依頼いただくことで、① 債権者からの督促がストップする(精神的に楽になる)、② 債権者との代理交渉をおこなってくれる、③ 手続きを任せることができる(事務処理の負担軽減)といったメリットがあります。
なお、借金問題に関する初回相談料は無料です。
法律相談は、電話(10分)、来所相談(60分)にておこなっています。
まずはお気軽に、電話やメールなどでお問い合わせください。
来所による無料相談では、家計やご希望を丁寧にお伺いしつつ、① 解決策のご提案、② 解決までの見通し、③ ご不安や悩みといった個別の質問への回答をおこなっています。
来所相談は随時WEBフォームでも受付中ですので、ご予約の上、ご相談ください。
© 2026 たちばな総合法律事務所