自己破産ができない場合と対処法~免責不許可事由や回避策を徹底解説~
個人破産
2025 . 09.2
個人破産
2025 . 09.2
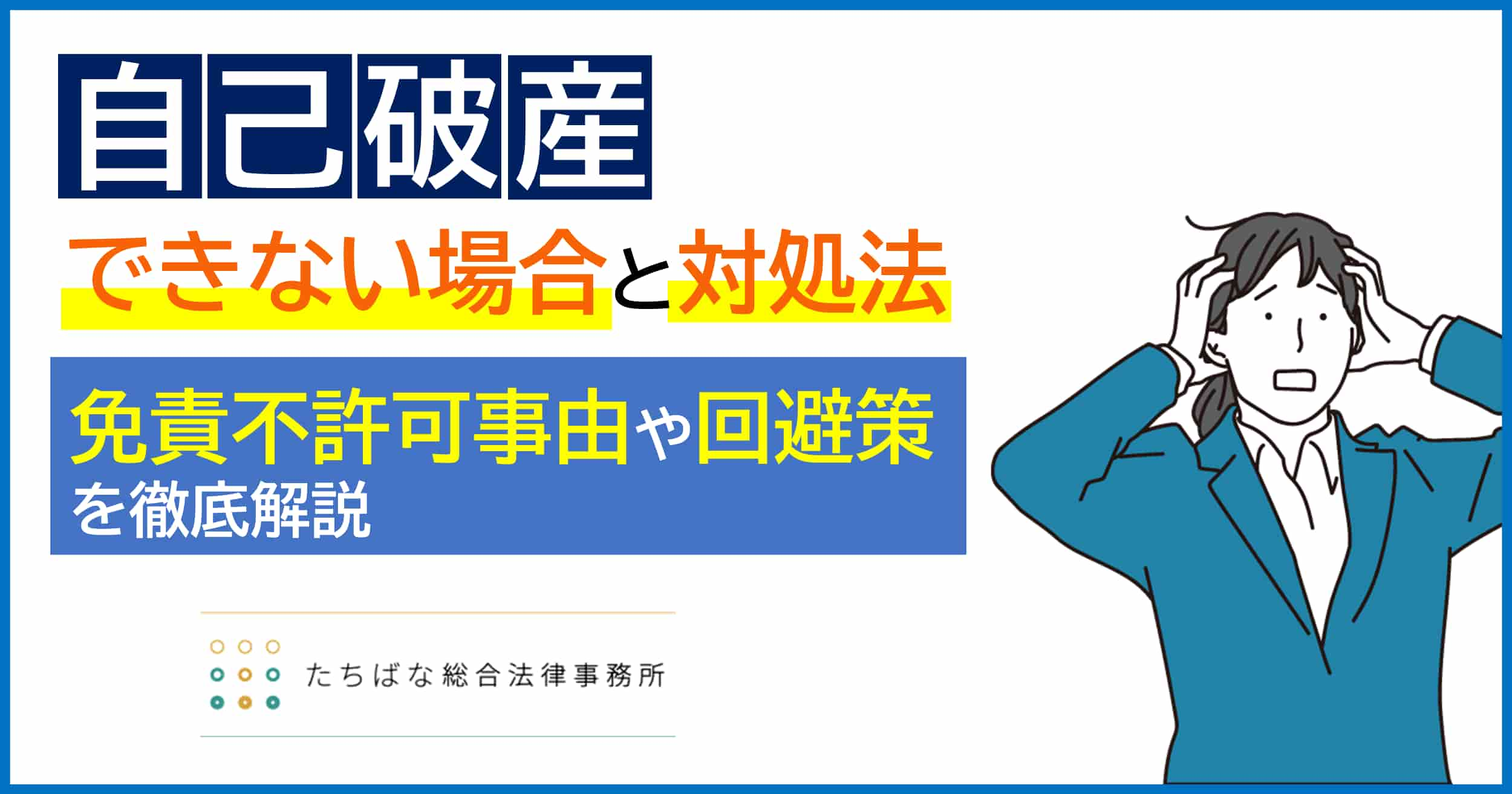
目 次
「借金が返せない…最後の手段として、自分は自己破産が利用できるのだろうか?」
「ギャンブルや浪費が原因だから、自己破産できないかもしれない…」
借金問題で追い詰められている方にとって、自己破産が認められるかどうか、非常に大きな不安があることでしょう。
しかし、結論から言えば、自己破産を申し立てた方の多くは、最終的に借金の支払いを免除(免責)されています。
たとえ免責が認められにくい事情(免責不許可事由)があったとしても、裁量免責という救済措置によって認められる可能性は十分にあります。
この記事を読んで不安を解消し、ご自身の状況に合った最適な解決方法を見つけるための一歩を踏み出してください。
まず、自己破産の基本的な仕組について解説します。
自己破産は、支払い不能におちいった債務者が裁判所に申し立てをおこなうことで、税金などの一部の債務を除き、合法的に借金の返済義務を免除してもらう制度です(破産法第253条1項)。
ただし、この手続きは2つの大きな関門をクリアする必要があります。
1 破産手続開始決定
裁判所が「この人は支払不能状態だ」と認める決定。
2 免責許可決定
裁判所が「借金の支払を免除する」決定。
このどちらかでつまずくと、「自己破産できない」という事態におちいります。
たとえば、借金総額が少ないのに安定した収入があり、返済が可能だと判断されれば、①の段階で申立てが認められない(棄却される)ことがあります。
また、手続きを進めるなかで、裁判所への提出書類や説明内容に虚偽(うそ)があると、②の段階で免責が認められないだけでなく、最悪の場合、詐欺破産罪(破産法第265条)という刑事罰の対象になる可能性すらあります。
裁判所や破産管財人(裁判所から選任され、財産調査や分配などを行う弁護士)には、すべてを正直に話す誠実な対応が免責許可決定を受けるうえで極めて重要です。
自己破産が認められるための大前提が、「支払不能」であることです。
これは、破産法で「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」(破産法第2条11項)と定義されています。
単に「生活が苦しい」「返済が厳しい」といった主観的な感覚や、一時的に経済状況が厳しいだけでは認められません。
裁判所が客観的に見て「この人にはもう継続的な返済能力がない」と判断する必要があります。
裁判所が支払い不能を判断する際は、以下のような事情を総合的に考慮します。
借金の総額、借入先、金利など。
給与、事業所得、年金など。負債返済が収入を超える状況か。
預貯金、不動産、自動車、生命保険など(20万円以上の価値がある高価なもの)。
家族構成や居住地に応じた支出か。
今後の収入見込み。自己破産後に生活を立て直すことができるか。
明確な基準はありませんが、一般的には「借金総額を3年(36回)で返済できない」状態であれば、支払い不能と判断される可能性が高いでしょう。
まずは本当に返済が不能なレベルかどうかを弁護士などの専門家に相談し、客観的な状況を把握することが大切です。
自己破産が認められるには、「支払不能」であることに加え、「免責不許可事由」に該当しないことが必要です。
たとえ支払不能状態であっても、これから説明する「免責不許可事由」が存在すると、借金の支払いを帳消しにしてもらう「免責」が認められない可能性があります。
免責不許可事由とは、破産法第252条1項に定められたルールのことです。
これは、債権者に多大な迷惑をかけながら、不誠実な行為をした債務者まで無条件に救済するのは公平ではない、という考えにもとづいています。
免責不許可事由については、あとでくわしく解説します。
上記以外にも、申立ての前提となる手続き上の要件もあります。
例えば、そもそも完済できる収入や資産があると判断された場合や、手続きに必要な費用(予納金)が用意できない場合、書類の不備がある場合などには、破産手続き自体が開始されません。
自己破産の手続きには、裁判所に納める費用(予納金)が必要です。このお金が用意できないと、手続きを開始することができません。費用が捻出できない場合は、法テラスの立替制度などを利用する方法があります。原則として、裁判所に納める費用は分割で支払うことができません。あらかじめいくらかかりそうか確認し、準備しておくようにしましょう。
申立書や添付書類に不備があり、裁判所からの補正命令に応じない場合、申立てが却下されることがあります。
これらの事由に該当しても、必ずしも自己破産をあきらめる必要はありません。
実際にどの程度の確率で自己破産が認められないのか、統計データや事例から見ていきます。
一般的には、自己破産申立ての多くは手続き開始に至り、免責も認められるケースが大半です。
しかし、裁判所の公表データを見ると、わずかとはいえ免責不許可となる事例があります。
自己破産が認められない原因としては、先ほど挙げた「書類の不備」による取り下げや「申立費用を用意できない」などの理由も含まれ、単純な免責不許可率だけでは全体が把握できないのが実態です。
いずれにしても、自己破産にあたり不安がある場合は、事前に弁護士に相談されると良いでしょう。
日本弁護士連合会(日弁連)がまとめた「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産を申し立てた個人のうち、最終的に免責許可決定が確定しなかったケース(免責不許可、取り下げなど)は、全体のわずか3.16%でした。
つまり、96%以上のケースでは、無事に免責が許可されていることになります。
数字が低いからといって油断はできませんが、免責不許可事由に心当たりがあっても、過度に不安になる必要はありません。
特に、買い物による浪費やクレジットカードの現金化など、比較的身近な行為で該当してしまった場合でも、その後の対応次第で十分に免責を得られる可能性はあります。
免責不許可ではなく、債務者側の都合で申立を取り下げるケースも存在します。
たとえば、以下のような状況です。
このような場合の債務整理方法として、自己破産に代えて任意整理や個人再生などの解決
方法に切り替えることを検討することになります。
具体的にどのような行為や状況が免責不許可事由に当たるのか、くわしく確認しておきましょう。
破産手続きにおける基本的な考え方は「債権者平等の原則」です。
これは、特定の債権者だけを優遇せず、すべての債権者をその債権額に応じて公平・平等に扱うという考え方です。
破産手続きは、債務者の財産がすべての借金を返済するには不足している状態(債務超過)で行われます。もし財産が十分にあれば、破産する必要はありません。
財産が足りない以上、債権者全員が100%の返済を受けることは不可能です。
そこで、債務者の残された財産(これを「破産財団」といいます)を全債権者で公平に分け合うことになります。
以下の行為は破産手続きの公平性を最も害する行為であり、裁判所に厳しく判断されます。
債権者への分配を免れる目的で、自分の財産を隠したり、壊したり、不当に価値を減少させたりする行為。例えば、預金を解約して現金で隠し持つ、自動車を友人名義に変更するなど。
財産を不当に安く他人に譲り渡す行為。
個人事業主などが、財産状況を分からなくする目的で、帳簿や書類を隠したり、偽の内容を記載したりする行為。
これらの行為は悪質と見なされやすく、裁量免責も認められにくい傾向にあります。
破産手続きを前提とした不誠実な資金調達も、免責不許可事由となります。
破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で借金をしたり、クレジットカードで商品を購入して著しく不利益な条件で処分(現金化)したりする行為。いわゆる「クレジットカードの現金化」がこれにあたります。
他の債権者を害する目的で、特定の債権者にだけ担保を提供したり、返済期日が来ていないのに返済したりする行為。親族や友人への返済が典型例です。
関連記事
「偏頗弁済とは?定義と正しい知識、やってはいけない返済のリスク」
支払い能力がないにもかかわらず、あるように見せかけて信用取引(ローン契約やクレジットカードの利用)を行い、財産を取得する行為。
免責不許可事由の中で最も一般的に知られているのが、この4号です。
収入や資産に見合わない過大な買い物、飲食、旅行など。
パチンコ、競馬などの賭博(ギャンブル)や、FX、株式投資などの投機的な取引で、著しく財産を減少させたり、過大な借金をしたりする行為。
これらが原因で借金を作った場合、免責不許可事由に該当します。
ただし、実務上は、この4号事由のみで直ちに免責不許可となるケースは少なく、本人の反省や更生の意欲、積み立てによる債権者への追加配当など、後述の裁量免責が認められることがあります。
破産手続きを円滑に進めるための協力は、申立人の義務です。
裁判所が行う調査において説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりする行為。
破産管財人がおこなう財産調査や管理などの職務を、詐欺や威力を用いて妨害する行為。
手続きに非協力的な態度は、反省していないと見なされ、裁判所や破産管財人の心証をいちじるしく悪化させるため、免責許可決定の判断に影響を及ぼす可能性があります。
過去に自己破産で免責許可決定が確定している場合、その確定日から7年以内に再度免責を申し立てても、原則として認められません。
また、個人再生の再生計画認可決定が確定してから7年以内の場合も同様です。
これは、短期間に繰り返し制度を利用することを防ぐための規定です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、裁判所の裁量で免責が許可される可能性もゼロではありません(2回目以降の自己破産)。
「免責不許可事由に当てはまってしまった…もう自己破産は無理なのか…」とあきらめるのはまだ早いです。
裁量免責という制度により、救済される可能性があります。
裁量免責とは、破産法上の免責不許可事由に該当する事実があったとしても、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」に、裁判官の裁量によって免責が認められる制度です(破産法第252条2項)。
実際、免責不許可事由があるケースでも、裁量免責によって救済されることがあります。
裁量免責は、破産法がもともと「債務者の経済生活の再生の機会の確保」(破産法第1条)を目的としていることから設けられた仕組みです。
裁判所が裁量免責を判断する際に重視するのは、主に以下の点です。
行為の内容や金額がどれほど過大か。
裁判所や破産管財人への説明が誠実か。
自身の行為を深く反省しているか。
今後、家計を改善し、二度と借金問題を起こさないという見込みや意欲があるか。
例えば、ギャンブルが原因であっても、専門機関で治療を受けている、家族のサポート体制が整っているなど、将来的に生活を立て直せる見通しを示せれば、裁量免責が適用される可能性は高まります。
悪質性が高いと判断されるケースでは、裁量免責が受けられる可能性は低いと言えます。
意図的に多数の財産を隠したり、債権者名簿に偽造を加えたりするなど、裁判所や債権者をだまそうとする行為。
申立て後もギャンブルを継続している、破産管財人からの電話や連絡を無視するなど、反省の態度が全く見られない。
浪費を重ねたうえに財産を隠し、さらに虚偽の説明を繰り返すなど、悪質な行為がいくつも重なっている場合
自己破産をしても支払義務がなくならない債務、いわゆる非免責債権(ひめんせきさいけん)について知っておきましょう。
自己破産で免責許可決定が確定すると、ほとんどの借金の支払義務はなくなりますが、一部の債権は政策的な理由から免責の対象外とされています(破産法第253条1項)。
これらの債務を抱えている人は、破産後も別途返済していく必要があります。
自己破産を申し立てる前に、自分の借金の中に非免責債権がどれくらい含まれているかを把握しておくことが非常に重要です。
代表的な非免責債権は以下の通りです。
所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料など。税金や保険料については、役所の窓口で分納や減免の相談をすることが一般的です。
詐欺や横領、暴力行為などによって生じた損害賠償。
飲酒運転による人身事故の損害賠償など。
意図的に隠していた債権者への債務。
破産手続きの免責の効力は、債権者名簿(債権者一覧表)に記載された債権者に対して及びます。
そのため、わざと記載しなかった債権者に対して、返済義務免除の効果は生じないことになります。
これらの債務を滞納すると、自己破産後であっても給与の差し押さえなどを受ける可能性があります。
もし借金の大部分が税金や養育費などの非免責債権である場合、自己破産をしても借金問題の根本的な解決にはなりません。
むしろ、破産手続きの費用だけがかかり、経済状況が改善しない恐れがあります。
このような場合は、自己破産以外の方法を検討するべきです。
弁護士や司法書士といった専門家に相談すれば、どの債務が非免責債権にあたるかを正確に判断し、自己破産のメリット・デメリットを踏まえた最適な解決方法を提案してくれるでしょう。
自己破産を選択することで逆に不利になる、あるいは手続きが認められない場合について知っておきましょう。
自己破産は、場合によってはデメリットが大きいケースがあります。
そのため、本当に自己破産がベストな選択なのかを慎重に判断する必要があります。
借金額が比較的少なく、3年~5年程度の分割払いで返済できる見込みがあるなら、自己破産以外の方法を検討する方が賢明な場合があります。
たとえば、任意整理であれば、将来利息をカットしてもらうことで月々の返済額を減らし、元本のみを無理なく返済していく計画を立てられます。
自己破産のように財産を失ったり、仕事への影響を受けたりするデメリットがありません。
自己破産の手続き中は、一部の職業で資格が制限され、業務をおこなえなくなります。
弁護士、司法書士、税理士など
生命保険募集人、警備員、貸金業務取扱主任者など
会社の役員(退任事由となる場合がある)など
これらの職業に就いている方が自己破産をすると、手続き中の収入が途絶えてしまうリスクがあります。
その場合は、資格制限のない任意整理や個人再生を選択する方が、生活への影響を抑えられます。
参考記事
「個人の自己破産のデメリット、メリットを徹底解説」
自己破産をおこなうと、原則として持ち家や自動車など、生活必需品を除き20万円以上の価値がある財産は処分の対象となり、破産財団に組み入れられて債権者への配当にあてられます。
「住宅ローンは残っているけれど、マイホームだけは手放したくない」という場合は、個人再生が有効な選択肢となります。
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、住宅ローンはそのまま支払い続け、それ以外の借金を大幅に圧縮することで、自宅を守りながら生活再建を図ることが可能です。
自己破産をすると、債務者本人の支払義務は免除されますが、その効果は連帯保証人には及びません。
連帯保証人は残った借金の全額を、債権者から一括で請求されることになります。
親や友人に保証人になってもらっている場合、その人の人生を大きく狂わせてしまう危険性があります。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人がついている債務だけを除外して手続きができる任意整理を選択するのもひとつです。
参考記事
「自己破産による連帯保証人への影響」
自己破産できない場合や避けたい場合、他の債務整理方法により借金を減らすことができるかもしれません。
自分の家計状況や目的、守りたい財産の有無に応じて最適な手段は変わってきます。
いざという時のために、複数の選択肢を知っておくことが大切です。
任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いの回数見直しなどを通じて、月々の返済負担を軽減する方法です。
交渉がまとまれば、3年~5年での分割返済計画を立てるのが一般的です。
個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を大幅に(通常は5分の1~10分の1程度に)圧縮してもらい、その減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
自己破産は避けたいけれど、任意整理では返済が難しいという場合に適した手続きです。
「過去、自己破産をし免責許可決定を受けた」
「自己破産の申立を取り下げた」
上記のような場合でも、事情によっては2回目の自己破産(免責許可決定)が得られる可能性はあります。
自己破産の手続きについてよくある疑問や、実際に起こりやすいトラブル例への対処法を紹介します。
A. 親族に援助を受けたり、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用する方法があります。
日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度は、収入などの要件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士費用の立替払いが利用できます。
立て替えてもらった弁護士費用などは、月々5,000円~10,000円程度の分割払いで返済していくことが可能です。
生活保護受給者の場合には、法テラスから立替金の返済免除を受けられる可能性があります。
また、弁護士事務所によっては、費用の分割払いに柔軟に対応してくれるところも多くあります。
弁護士に依頼すれば、債権者からの督促が止まるため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積み立てに回すことができます。
費用面で不安な場合も、まずは相談してみることが重要です。
A. 自己破産をしても、家族や勤務先に知られるリスクは、多くの方が心配するほど高くはありません。
手続きをすると、国の広報誌である「官報」に氏名と住所が掲載されますが、日常的に官報をチェックしている一般の人はほとんどいません。ここから知られる可能性は極めて低いでしょう。
ただし、以下のようなケースでは知られる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、書類の送付先を事務所に指定するなど、家族に知られないよう最大限配慮して手続きを進めてくれます。
A. 実際に免責不許可となった事例には、多額のギャンブル債務を隠して申立てを行ったケースや、破産管財人の調査に協力せず、虚偽の説明を繰り返したケースなどがあります。
一度免責不許可の決定が下されると、重い借金がそのまま残るため、極めて厳しい状況に陥ります。
万が一、免責不許可の決定が出てしまった場合でも、即時抗告という不服申立ての手続きが可能です。
決定から1週間以内という短い期間内に、高等裁判所に対して再度審理を求めることができます。
それでも決定がくつがえらない場合は、個人再生への切り替えを検討したり、地道に返済を続けていくほかありません。
債務問題は一人で抱え込むにはあまりに複雑で、精神的な負担も大きいものです。
できるだけ早く専門家へ相談することが、解決への確実な一歩となります。
自己破産ができない理由には、「支払不能」と認められないケースと、「免責不許可事由」に該当するケースの2種類があります。
特に、浪費やギャンブル、財産隠しなどの行為は、免責が認められない原因となり得ます。
しかし、たとえ免責不許可事由に心当たりがあっても、95%以上のケースでは裁量免責によって最終的に借金は免除されています。
諦めずに、まずは弁護士などの専門家に正直に状況を話すことが大切です。
もし自己破産が難しいと判断された場合でも、任意整理や個人再生といった他の解決策があります。
専門家は、あなたの状況を客観的に分析し、守りたい財産や保証人への影響なども考慮した上で、最も適した方法を提案してくれます。
たちばな総合法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。
法律相談は、電話(10分)、来所相談(60分)にておこなっています。
まずはお気軽に、電話やメールなどでお問い合わせください。
来所による法律相談では、家計やご希望を丁寧にお伺いしつつ、① 解決策のご提案、② 解決までの見通し、③ ご不安や悩みといった個別の質問への回答をおこなっています。
来所相談は随時WEBフォームでも受付中ですので、ご予約の上、ご相談ください。
なお、お問い合わせ自体も外部に漏れることはありません。
安心して、お問い合わせ、ご相談ください。
© 2025 たちばな総合法律事務所