会社員(サラリーマン)が自己破産する際に知っておきたいすべてのポイント
個人破産
2025 . 05.15
個人破産
2025 . 05.15
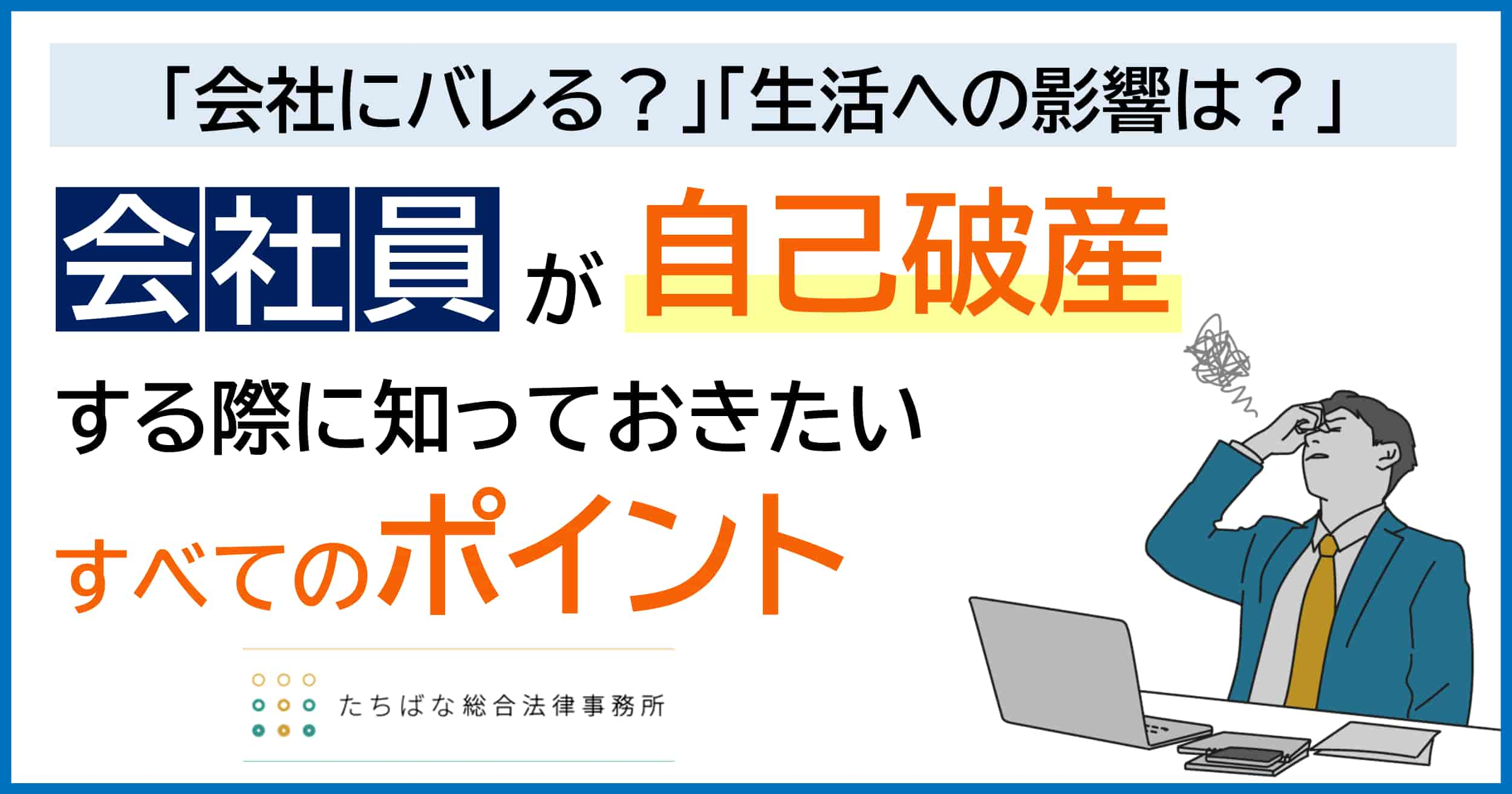
この記事でわかること
 たちばな総合法律事務所 代表
たちばな総合法律事務所 代表 たちばな総合法律事務所
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
目 次
会社員として働きながら借金の返済が難しくなったとき、自己破産は最終的な債務整理の手段として選択されることがあります。
しかし、自己破産は借金を免除してもらう反面、所有財産の処分や官報に破産の事実が掲載されるなど生活や仕事への影響があります。
本記事では、自己破産の手続きの流れや財産処分、会社に知られる可能性、解雇や懲戒処分のリスクはあるのか、就職への影響などを、会社員が押さえておきたいポイントや注意点について網羅的にまとめて解説しています。
会社員が自己破産を検討する場合、まずは自己破産の基本的な仕組みや、他の債務整理の手続きの概要を知ることが大切です。
自己破産手続きは、借金の返済が不可能な状態になった人が、地方裁判所に申立てをおこない、法律に基づいて借金の支払い義務を免除(免責)してもらうことで、経済的な立ち直りを図るための手続きです。
破産手続の開始決定時に一定以上の価値のある財産を所有している場合や、借金の原因に問題がある場合(浪費やギャンブルなど)は、管財事件となり、破産管財人が選任されて財産の調査・処分がおこなわれます。
一方、換価するような財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合は同時廃止事件として、比較的簡易な手続きで終了します。
自己破産の最大のメリットは、原則として全ての借金の支払い義務がなくなる点が挙げられます。
ただ、税金や子どもの養育費などの非免責債権は免除されません。
参照 非免責債権の例
1. 税金、年金、健康保険料などの公租公課
2. 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3. 故意または重大な過失により加えた、
人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4. 養育費や婚姻費用(夫婦間の生活費)
5. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料
自己破産のデメリットは、債権者への配当に充てるために、持ち家や車など、一定額以上の財産処分が必要であること、官報に氏名・住所が掲載されること、信用情報機関に事故情報として登録され、約5年~10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成などが難しくなること、連帯保証人がいる場合、保証人に請求がいくことなどが挙げられます。
自己破産の主な手続きの流れは、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、申立書を作成・提出するところから始まります。
裁判所が手続きを受理すると、借金の状況や所有財産を調査する段階に入り、管財事件か同時廃止事件かが決定されます。
管財事件では破産管財人が財産の処分や債権者への配当を行い、同時廃止事件では処分すべき財産がないか極めて少ないと判断されるため、比較的早く免責決定が下りやすい傾向にあります。
最終的に裁判所が免責を認めれば、対象となる借金は支払義務が免除されます。
これにより、新たなスタートを切ることができます。
自己破産のデメリットの一つに資格制限が挙げられます。
生命保険の外交員(生命保険募集人)、警備員、旅行業務取扱管理者などは破産手続開始決定があると資格制限を受けるため、就業に影響が出る可能性が高いです。
また、会社の取締役の場合、会社との委任契約が破産開始決定により終了するため退任することになります。
こうした場合、自己破産以外の任意整理、個人再生といった債務整理手続きを検討することがあります。
任意整理は、債権者と直接交渉し、今後の借金の返済方法について和解契約を結ぶことで、借金の負担を軽減する手続きです。
多くのケースでは、将来利息のカットや長期の分割払いの合意を得ることで、月々の返済額や返済総額を減らすことを目的に交渉がおこなわれます。
ただし、元金自体を大幅に減額する手続きではなく、また合意に応じない債権者がいる場合、交渉自体ができない点にも注意が必要です。
個人再生手続きは、借金の返済が困難になった人が、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額してもらい、原則として3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割して返済していく手続きです。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、ローンのある住宅などの財産を維持しながら負債を整理できる可能性がある点が大きな特徴です。
任意整理、個人再生のいずれも、自己破産と違い、返済を基本とする負債整理であるため、安定した収入が必要になります。
会社員の方が気になるのが、自己破産をすることによる給料やボーナス、退職金や、所有財産の取り扱いです。
給料や賞与には法律上の差し押さえ禁止額が定められており、手取り金額の4分の3は差し押さえが禁止されています。
賞与は、すでに支給が確定している分だけでなく、将来支給される予定の賞与についても、差し押さえ命令の時点で差し押さえの対象となり得ます。
自己破産を申立て、裁判所が破産手続開始決定を出す前に給料の差し押さえを受けていた場合には、破産開始決定が出されるとその差し押さえ失効(中止)するのが原則です。
これにより、以降の給料は差し押さえの対象から外れます。
なお、自己破産により免責許可が確定すると、原則として借金の支払い義務はなくなります。
そのため、免責された借金を原因とする給与差押えを新たに受けることはありません。
ただし、自己破産によっても支払い義務がなくならない「非免責債権」(税金、養育費、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務など)については、免責後も支払い義務が残るため、これらの債権を滞納した場合には、給与を含めた財産が差し押さえられる可能性があります。
税金などの公租公課は、裁判所の手続きを経ずに差し押さえが行われることもあるため注意が必要です。
破産手続開始決定後に受け取る給料や賞与は「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれ、原則として申立人が自由に使うことができます。
自己破産では、一定の価値を持つ財産が裁判所や破産管財人によって処分対象となる可能性があります。
具体的には、時価の高い自動車や高額の退職金、住宅ローン残高がありながらも資産価値のある不動産などが該当します。
さらに、財形や社内預金制度を利用している場合には、通常の預金と同様に会社員の財産として扱われますので、後記の自由財産を超える部分については、これらも処分を余儀なくされます。
ただし、自由財産と認められる一定範囲の現金や生活必需品は処分の対象から外れるケースが多く、日常生活に必要不可欠なものは手元に残ることが一般的です。
退職金については、破産手続開始決定時点での状況により取り扱いが変わります。
① すでに退職金を受け取っている場合
すでに退職して退職金を受け取り、現金や預貯金として手元にある場合は、その退職金は現金や預貯金といった形で破産財団に含まれる財産として扱われます。
99万円以下の現金や、一定額以下の預貯金など、法律で定められた自由財産として手元に残せる範囲を超過する部分は、原則として処分が必要になり、債権者への配当に充てられます。
② まだ在職中で退職金を受け取っていない場合
将来退職金を受け取る権利(退職金債権)がある場合、自己破産の手続き上、その退職金債権も破産者の財産として扱われます。
しかし、まだ退職金を受け取っていないため、その全額が直ちに処分されるわけではありません(退職や、現金化を求めることはありません)。
多くの裁判所では、自己都合退職を仮定した場合の退職金見込額の8分の1を、破産財団に組み入れを求めるのが一般的です(ただし、裁判所や具体的な状況によって判断が異なる場合があります)。
実際に退職してその金額を支払うのではなく、申立人が自己資金や自由財産の中からその相当額を準備して破産管財人に引き渡す、あるいは親族からの援助を受けるなどの方法で対応することが多いです。
③ 近いうちに退職予定である場合
自己破産の手続き中に退職が間近に迫っているなど、近い将来退職金を受け取ることが確実であると見込まれる場合は、退職金見込額の8分の1ではなく、4分の1が財産として扱われる運用がされることもあります。
これは、退職金を受け取れる可能性が高いため、財産としての価値をより高く評価するためです。
「自己破産で生命保険の解約が必要な場合と、契約を維持するための4つの方法」
生命保険契約における解約返戻金の取り扱いについて、詳しく解説してます。
解約返戻金額が一定額を超える見込みがある場合には、その金額に相当する金額を破産管財人に引き渡すよう指示を受ける可能性があります。
「自己破産でどれくらい手元に財産・家財道具は残せるの?(自由財産について解説)」
個人の破産手続きにおいて、どの程度の範囲まで手元に財産を残すことができるかについて解説しています。
自己破産は官報に掲載される手続きのため、会社に知られるリスクがゼロとは言い切れません。
会社が債権者になっている場合はもちろん、退職金見込額の計算書が必要になるといった手続き上の事情で、勤務先と連絡を取ることが避けられないケースもあります。
もっとも多いのは、勤務先が借入先(債権者)の一つになっているケースです。
財形貯蓄や、社内預金を解約せずに保持している場合も、解約を余儀なくされますので、解約の申し入れが端緒となり会社に発覚する場合もあります。
この場合、自己破産手続きの申立時に必ず会社を債権者として裁判所に申告する必要があり、裁判所からも会社側に通知が届くため、必然的に事情が知られることになります。
官報とは日本における機関紙です。
自己破産により官報に掲載されるのは「住所」「氏名」が掲載されます。
官報掲載を日常的にチェックする企業はそれほど多くないため、掲載をきっかけに会社に破産の事実を知られる可能性は低いと言えます。
ただし、金融機関や同業の一部企業などは業務上独自に調査を行う場合があり、それをきっかけに情報が社内に伝わることも否定できません。
また、必要な書類を揃える過程で会社に協力を求めざるを得ない場合もあり、そのやり取りを通じて破産手続きが発覚するケースもあるため、事前の対策と検討が重要です。
自己破産によって会社から解雇や懲戒処分を受けるのではないかと心配する方は少なくありません。
ここでは、自己破産が原因で解雇、懲戒処分を受ける可能性があるかどうかについて解説します。
自己破産だけを理由に解雇することは、会社の解雇権の濫用であるとみなされ、「不当解雇」に当たるとされ、原則として無効となります。
ただし、自己破産に至る経緯や、自己破産によって会社に具体的な損害(例:会社の信用を著しく失墜させた、業務上横領などが破産の原因である場合など)が発生しているような特別な事情がある場合は、個別のケースによって解雇が有効と判断される可能性があります。
自己破産によって他部署へ異動となる場合(配置換え)や、一部業務の担当を変更される可能性があります。
例えば、自己破産による資格制限がある職種(弁護士、公認会計士、警備員など、破産手続開始決定から免責許可決定が確定し復権するまでの期間、法律によりその業務への従事が制限される職業)に就いている会社員の場合、破産手続中は法律上その資格に基づく業務をおこなうことができません。
そのため、配置換えや、配置換えにともなう減給を受ける可能性があります。
・配置換え(配置転換)
資格制限により従事できない業務から、別の部署や職務への配置換えを命じられることがあります。
これは、会社が従業員に対して持つ業務命令権に基づきおこなわれるものであり、資格制限によって従来の業務遂行能力が一時的に失われている状況においては、業務上の必要性があると認められやすく、原則として適法となる可能性が高いです。
ただし、配置換えがあまりにも不合理なものであったり、嫌がらせ目的と判断されるような場合は、権利濫用として問題となる可能性があります。
・減給
配置換えや降格に伴い、担当する職務内容の責任や重要度が変わることで、給与が減額される可能性はあります。
これは、変更後の職務内容に見合った給与額に見直すという性質を持つため、配置換えと同様に、直ちに不適法とは言えない場合があります。
しかし、単に自己破産したことのみを理由とする不当な減給や、変更後の職務内容と比較して不相当に大きな減給は認められません。
これらの配置換えや減給が「自己破産したこと自体」に対する懲罰的な措置なのか、それとも「資格制限によって一時的に特定の業務に従事できなくなったこと」に伴う、業務上の必要性に基づいた合理的な人事上の措置なのかという点は検討が必要です。
そのため、資格制限により業務遂行が不可能になった関係から、配置換えや、それに見合った範囲での減給については、適法と判断される可能性があります。
自己破産が転職や新卒採用に対してどのような影響があるかについて解説します。
一般的に、自己破産による転職や就職への影響がありません。
ただ、資格を備えることが採用、就業の条件となっているような場合、自己破産により資格制限を受けることで採用に影響が生じる可能性は大いにあります。
弁護士や司法書士が士業事務所などに就職する場合、警備員としての採用や保険募集人の資格をもってする生命保険会社の営業職への就職において、影響がある可能性があります。
こうした資格制限を原因とする減収が心配される場合、そのリスクを回避するために個人再生を利用されるケースも多くあります。
将来に渡って安定した収入や、負債の大幅な減額を見込めることから利用しやすい手続きといえます。
基本的に、自己破産を含む個人的な債務整理の情報を採用時に企業へ申告する義務はありません。
なお、就職先や採用面接先である金融機関が、採用を目的に個人信用情報を閲覧することはできません。
会社員として日々の生活を維持しながら借金問題を解決するには、自分の状況に合った手段を選択することが重要です。
どうしても返済が困難な場合には自己破産は最終手段となりますが、正しい知識を持ったうえで、弁護士などの専門家に相談し、他の債務整理方法も含めてベストな解決策を探されることをおすすめします。
たちばな総合法律事務所では、生活再建に向けた個人の方の負債整理(個人再生・自己破産・任意整理)についてサポートしています。
破産管財人の経験を持つ、解決実績たしかな弁護士が相談から手続きが終結するまで、しっかり対応いたします。
弁護士にご依頼いただくことで、① 債権者からの督促がストップする(精神的に楽になる)、② 債権者との代理交渉をおこなってくれる、③ 手続きを任せることができる(事務処理の負担軽減)といったメリットがあります。
なお、借金問題に関する初回相談料は無料です。
法律相談は、電話(10分)、来所相談(60分)にておこなっています。
まずはお気軽に、電話やメールなどでお問い合わせください。
来所による法律相談では、家計やご希望を丁寧にお伺いしつつ、① 解決策のご提案、② 解決までの見通し、③ ご不安や悩みといった個別の質問への回答をおこなっています。
来所相談は随時WEBフォームでも受付中ですので、ご予約の上、ご相談ください。
なお、お問い合わせ自体も外部に漏れることはありません。
安心して、お問い合わせ、ご相談ください。
© 2026 たちばな総合法律事務所