自己破産はいくらからできる?支払不能かどうかを判断する基準と手続きの要点
個人破産
2025 . 09.1
個人破産
2025 . 09.1
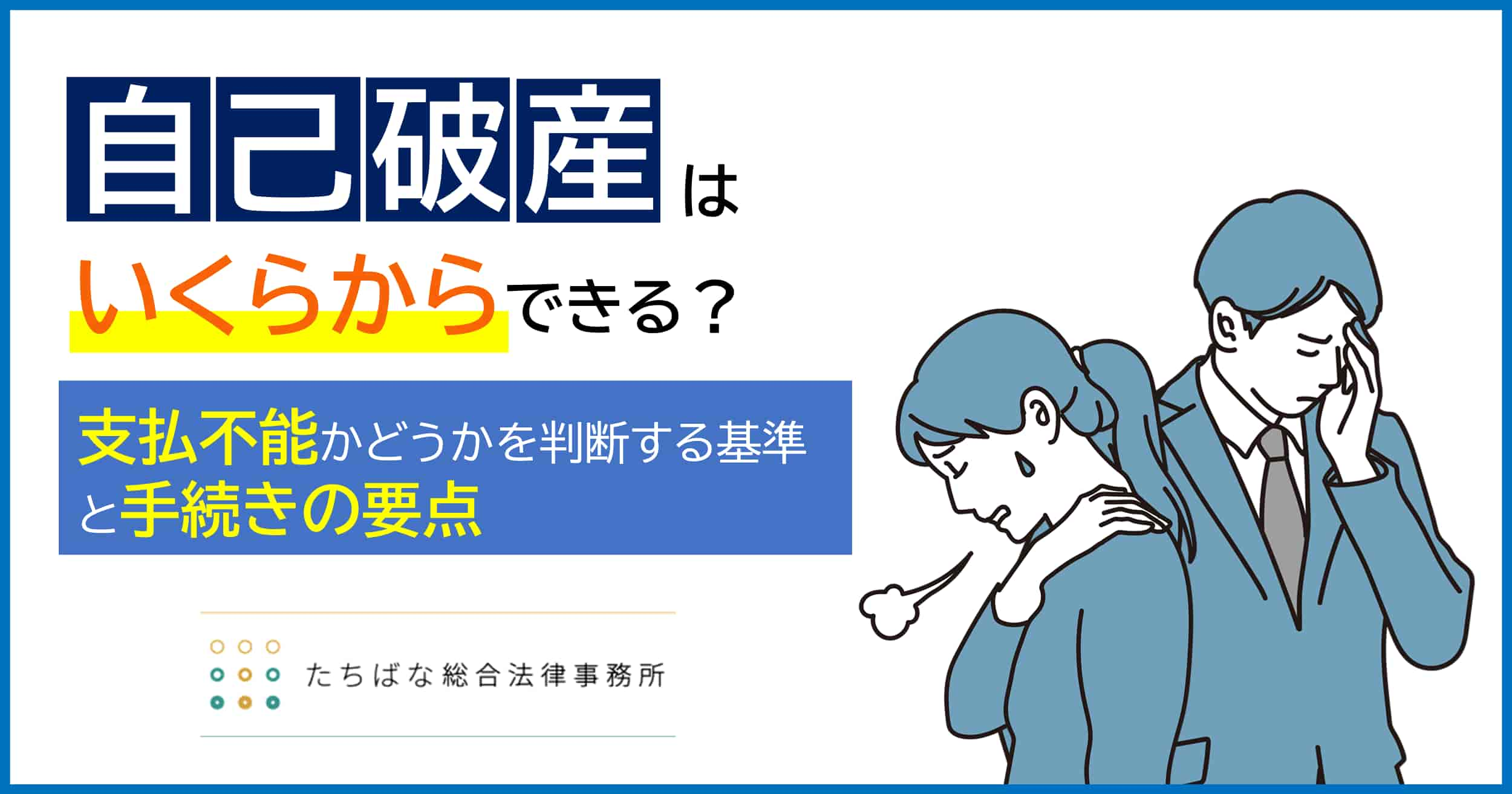
返済の見通しが立たない借金を法的に整理する手段として、「自己破産申立」は多くの方が利用しています。
自己破産は「借金がいくらあれば利用できる」という法律上の基準はありません。
収入を大幅に超える債務超過状態で、返済が難しい状況にあれば利用可能と考えられます。
たとえば、生活保護を受けている方で、100万円未満の借入れであったとしても、返済の目途が立ないような時には債務超過状態にあると言え、破産をおこなうことが十分に可能であると考えらえます。
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、法律に基づいて借金の返済義務を免除してもらう制度です。
裁判所から「免責決定」が下りると、借金の返済が免除されるのが最大のメリットです。連帯保証人になっている場合の保証義務も対象となります。
ただし、離婚時の養育費や税金など、一部の支払いは免除されません。
一方で、自己破産には以下のようなデメリットもあります。
「自己破産」という言葉の響きや、上記のようなデメリットから、手続きをためらう方も少なくありません。
しかし、借金の返済義務がなくなるというメリットは、生活を立て直すための非常に大きな支えとなります。
もちろん、債務整理の方法は自己破産だけではありません。
借金問題で悩んでいる場合は、まず弁護士や司法書士など法律の専門家に相談し、ご自身の状況に最も合った解決策を見つけることが大切です。
自己破産を申し立てるためには、法律上の「支払不能」と認められる必要があります。
これが最も重要な条件です。
支払不能とは、支払能力を欠くため、収入や資産をもってしても借金を継続的に返済し続けることが事実上不可能な状態を指します。
簡単に言うと、ご自身の収入や財産では、どう考えても借金を継続的に返済していくことが事実上不可能な状態を指します。
「今月だけ返済が苦しい」といった一時的な資金不足は、支払不能にはあたりません。
今後の収入の見込みや家計の状況なども含めて、「この先も返済を続けるのは客観的に見て無理だ」と判断される必要があります。
「今月だけ返済が苦しい」といった一時的な資金不足や返済の遅れは、支払不能にはあたりません。
今後の収入の見込みや家計の状況、資産の有無なども含めて、「この先も返済を続けるのは客観的に見て無理だ」と判断される必要があります。
お給料などの収入はあっても、借金の総額が大きすぎて、毎月の返済で生活が成り立たなくなっている状態です。
返済をしたら、家賃を払ったり食事をしたりという最低限の生活もできなくなる、といった場合は、裁判所が「支払不能」と判断する可能性が高くなります。
また、無職・失業中で無収入であり、この先も安定した収入が得られる見込みが立たない状態も、支払不能と認められる可能性が高いと言えます。
弁済期、つまり返済日が来ているにも関わらず、借金について返済できない状態にあることが必要です。
裁判所は、単に一時的に現金が不足しているだけでなく、今後も継続的に返済の見込みがないことを重視します。
例えば、ケガや病気で生活がままならず、安定した収入が見込めない場合などは支払不能だと判断されやすいでしょう。
本コラムのはじめにお伝えしましたが、自己破産について、法律上、借金が何万円以上でないと申立てできないといった明確な基準はありません。
自己破産は、支払不能の状態であれば少額の借金でも申立てができます。
例えば、日本弁護士連合会によるサンプリング調査「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、自己破産された方で「負債100万円未満」は8.39%となっており、一般的に少額と言えそうな金額であっても、破産手続きが利用されていることが分かります。
出典:日本弁護士連合会「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」
30万円程度の借金でも、まったく収入がなく返済の見込みがない場合は自己破産を検討するケースもあります。
ただ実情としては、裁判所や弁護士費用を含めた総合的なコストや負担を考えた結果、少額の場合には任意整理など他の債務整理を選ぶ人も多いようです。
質問としてよくあるのは「いくらから自己破産できるか」という点ですが、結論としては法的に金額の下限は設定されていません。
大切なのは自身の資産や収支を踏まえ、継続的に返済できない状況かどうかを冷静に判断することです。
自己破産を申し立てても、必ず借金が全額免除されるとは限りません。
どのようなケースだと免責を受けられないのか。
法律上、免責が認められないケースでも、裁判所の判断で認められる可能性はあるのか(裁量免責)ついて解説します。
法律上、次のケースに当てはまる場合には、免責が認められないとされています。
裁判所は、破産を申し立てた人(破産者)に以下の事由が一つもない場合か、または仮に以下の事由があっても後記の裁量免責が認められる場合hに、借金の返済義務を免除する「免責許可決定」を出します。
逆に言えば、以下のいずれかに該当する行為があると、原則として免責は許可されません。
こうした行為によって作られた債務は、裁判所が「本人の責任が重い」と判断する可能性があるため、免責が認められない場合があります。
ただし、免責不許可事由に当てはまる債務であっても、最終的には裁判官の裁量で免責が認められる可能性が残されています。
裁量免責は、法律上不許可とされるケースであっても、借金を抱えた個人を再生させる社会的意義を重視して適用される制度です。
裁判官は、申立人の反省や経済的状況、今後の見通しなどを総合的に判断します。
特に初めての自己破産の場合や、反省の態度が見られる、再度の浪費を防ぐための努力が明確にあると認められた場合などに、裁量免責が下りる可能性はあります。
個人の自己破産にかかる費用は、大きく分けて①必要書類の収集費用、②裁判所へ納める費用、③専門家(弁護士・司法書士)への依頼費用の3つです。
費用の目安: 数千円程度
住民票や課税証明書などを役所で取得する際の実費です。1通あたり300円〜750円程度かかります。
費用の目安: 1,500円
収入印紙を購入し、申立書に貼り付けて納付します。
費用の目安: 3,000円~15,000円
裁判所から債権者への書類送付などに使われる郵便切手代です。裁判所や債権者の数によって変動します。
費用の目安: 1万円~50万円以上
手続きの種類によって金額が大きく異なります。
① 同時廃止: 1万円~3万円
② 管財事件(少額管財): 20万円~
③ 管財事件(通常管財): 50万円~
費用の目安: 30万円前後~
手続きが複雑な管財事件の方が高くなる傾向があります。多くの事務所で分割払いに対応しています。
費用の目安: 25万円前後~
書類作成の代行が主な業務です。弁護士と異なり代理人にはなれないため、裁判所とのやり取りは本人が行う必要があります。
裁判所に納める費用には、「申立手数料(印紙代)」や「予納郵券(郵便切手代)」などがありますが、これらは合計しても2万円程度です。
最も金額が変動するのが「予納金」で、これは自己破産手続きの種類によって大きく異なります。なお、どの破産手続きで進むのかは、裁判所の判断によります。
手続きを専門家に依頼する際の費用は、弁護士か司法書士か、また事案の複雑さによって変わってきます。
弁護士費用の相場は30万円程度~で、管財事件になると高くなる可能性があります。
これらの費用を一括で支払うのが難しい場合でも、国が設立した「法テラス」の立替制度を利用したり、多くの法律事務所が費用の分割払いに応じてくれることがあります。
まずは諦めずに専門家へ相談することが、生活再建への第一歩です。
関連記事
「法テラス利用で自己破産する方法」
自己破産を「できない」または「すべきでない」ケースがあります。
こうした場合、どのように対応するべきかについて解説します。
先ほど説明した通り、ギャンブルや浪費が原因で多額の借金を作ったり、特定の債権者にだけ返済したり、財産を隠したりするなどの「免責不許可事由」に該当する場合、裁判所は原則として借金の免除(免責)を認めません。
この場合は法的に自己破産ができません。
法律上の問題はなくても、以下のような方は自己破産のデメリットが大きいため、他の方法を検討すべき場合があります。
自己破産の手続き中は、弁護士、司法書士、警備員、保険募集人など、一部の職業の資格が制限され、その職に就くことができない期間が発生します。
仕事への影響が大きい方は慎重な判断が必要です。
自己破産では、持ち家や車など価値のある財産は原則として全て手放す必要があります。「家だけは残したい」という希望がある場合、自己破産は向いていません。
自己破産をすると、本人の返済義務はなくなりますが、その請求は全て保証人・連帯保証人にいきます。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、他の方法を検討する必要があります。
自己破産には裁判所費用や専門家費用で少なくとも30万円以上かかります。例えば借金がそれよりも少額の場合、費用をかけて自己破産するよりも、他の方法で返済を目指す方が合理的な場合があります。
自己破産以外にも、任意整理や個人再生などの債務整理方法があります。
まずは自分の状況において、他の選択肢がないか専門家と一緒に検討されることおすすめします。
自己破産が難しい場合には、主に「個人再生」と「任意整理」という2つの方法があります。
任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉します。
将来かかる利息(将来利息)や遅延損害金をカットしてもらい、残った元本を3年~5年で分割返済する和解を目指す手続きです。
裁判所を通さないため比較的スピーディーに進められますが、利息の減額幅などは交渉によるため、やはり弁護士などの専門家の協力が必要になります。
参照
手続きが最も簡単
裁判所を通さないため、期間が短く費用も安価です。
整理する借金を選べる
保証人がいる借金だけを除外して、他の借金だけを整理するといった柔軟な対応が可能です。
財産を手放す必要がない
財産処分は不要で、資格制限もありません。
元本は減らない
減額されるのは将来の利息が中心で、借金の元本は基本的に減りません。
安定収入が必要
元本を3年~5年で返済できるだけの、毎月安定した収入がなければ利用は困難です。
裁判所に申し立て、借金を約1/5~1/10に大幅に減額してもらい、その金額を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
個人再生は、住宅ローンの返済は従前の契約どおり支払うことで、持ち家を手元に残すことができます。
自己破産では、債権者は平等に取り扱い、配当をおこなう必要がありますが、個人再生では住宅ローン債権者(金融機関)については、別途支払うことが可能です。
ただし、定期的な収入があることが前提となり、計画通りの支払いができなければ再生計画が失敗する可能性もあるので注意が必要です。
住宅を守りながら借金問題を解決したいと考えるなら、個人再生が有力な選択肢となるでしょう。
参照
持ち家を残せる
「住宅ローン特則」という制度を使えば、持ち家を手放さずに他の借金を減額できます。
資格制限がない
自己破産のような職業の制限はありません。
借金の理由は問われない
ギャンブルや浪費が原因でも利用可能です。
返済義務は残る
借金はゼロにはならず、継続的な返済が必要です。
手続きが複雑
費用も自己破産(管財事件)と同程度か、それ以上かかる場合があります。
各債務整理手続きの比較は次のとおりです。
自己破産: 全額免除(ゼロになる)
個人再生: 大幅に減額(約 1/5 〜 1/10)
任意整理: 将来利息のカットが中心
自己破産: 原則すべて手放す
個人再生: 家などを残せる可能性がある
任意整理: 財産を手放す必要なし
自己破産: あり
個人再生: なし
任意整理: なし
自己破産: 全額請求される
個人再生: 全額請求される
任意整理: 対象から外せる
自己破産: 必要
個人再生: 必要
任意整理: 不要(直接交渉)
自己破産:
・返済能力が全くない
・高額な財産がない
個人再生:
・家を残したい
・継続的な収入がある
任意整理:
・借金が比較的少額
・保証人に迷惑をかけたくない
自己破産は、借金をゼロにできる強力な制度ですが、申立てが認められるためには条件を満たす必要があります。
具体的な下限額は設けられていない一方で、少額の借金だと費用面やデメリットを考慮して他の債務整理方法を検討する余地があるのも事実です。
また、ギャンブルや浪費による借金でも、反省や再起の意思を示せば裁量免責が認められる可能性があります。
手続き費用の負担が難しいときは、法テラスの立替制度や分割払いといった対策も利用可能です。借金問題は放置すると深刻化していくため、専門家と協力しながら速やかに最適な債務整理方法を探ることをおすすめします。
たちばな総合法律事務所では、個人の方の借金問題について、初回無料法律相談をおこなっています。
初回相談では、① あなたに最適な解決策、② 解決までに流れなどについてアドバイスをおこなっています。個別の不安や疑問に対する質問にもお答えいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
© 2025 たちばな総合法律事務所